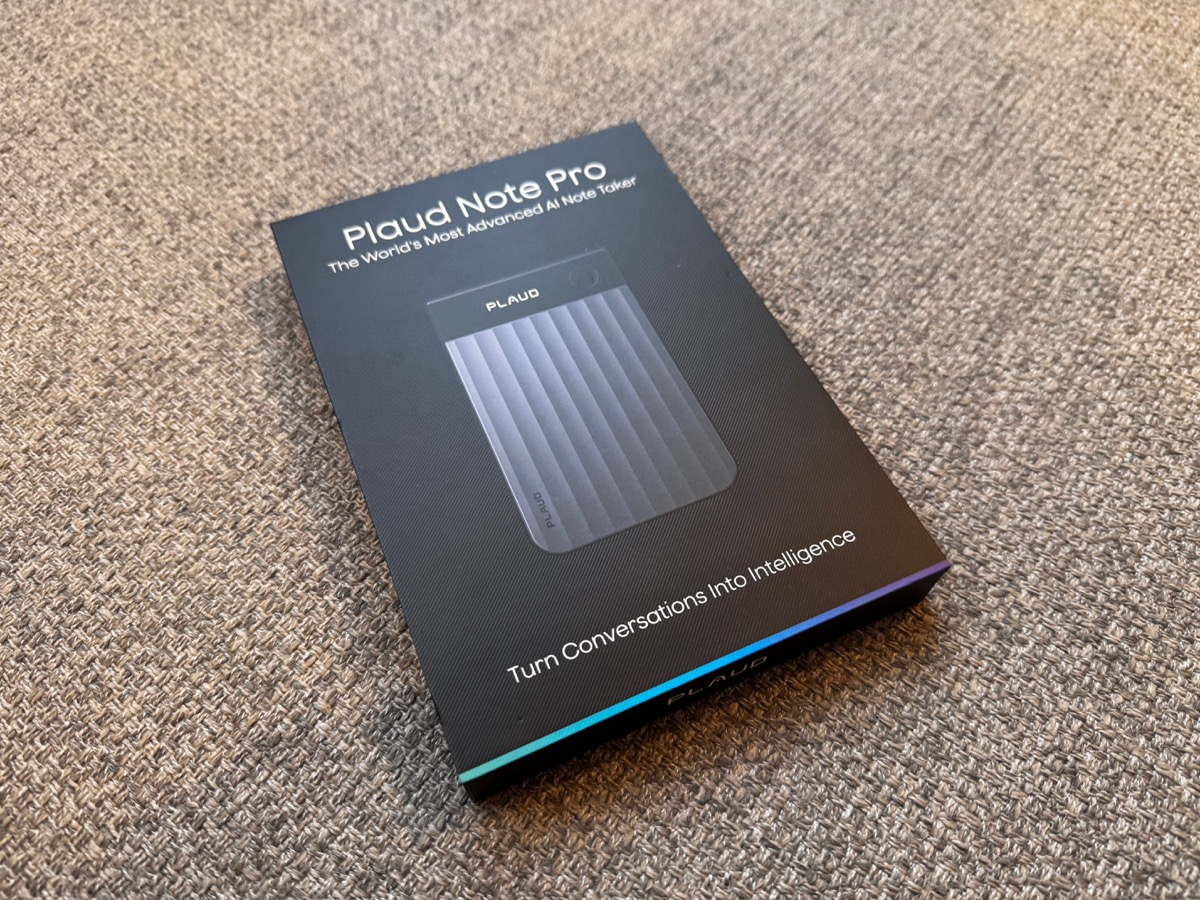「プロンプトエンジニアリング」はもう要らないって?
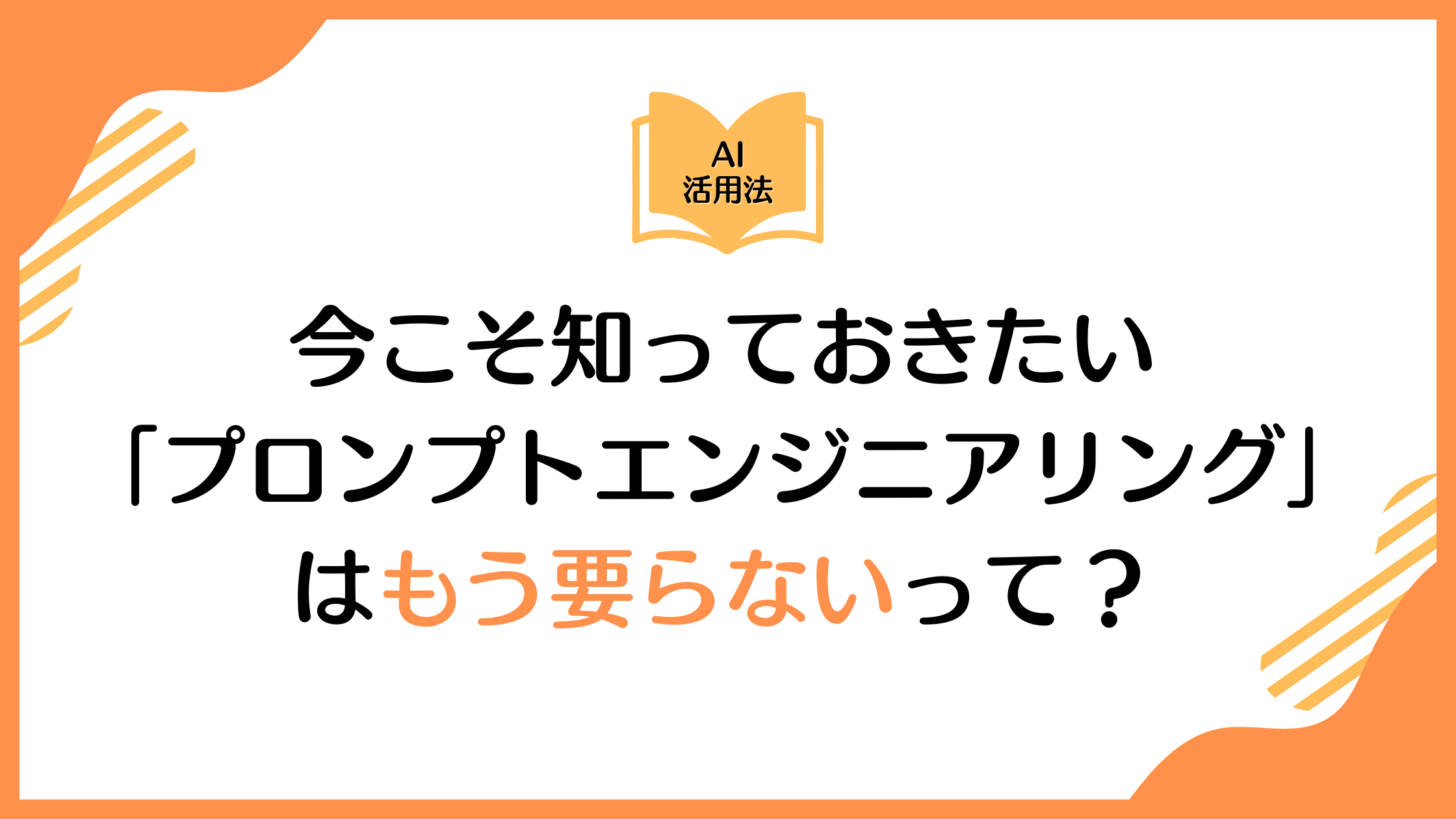
「AIを使いこなすには、”プロンプトエンジニアリング”が必須」。 そんな言葉をよく聞く。まるでAIという巨人を動かすための「秘密の呪文」みたい。でも、僕らビジネスパーソンからすると、その「呪文」を覚えること自体が、正直”難しい”と感じない?
「AI活用」って聞くとワクワクするのに、「プロンプト」って言葉が出た瞬間に、急に専門知識の壁を感じて一歩引いてしまう。僕もまさにそうだった。
でもね。もし、その難解な「呪文」自体を、AI自身に作らせることができるとしたら……? 今日はそんな、AIとの付き合い方がガラッと変わるかもしれない「ある実験」と、そこから見えた未来についての話をしようと思うんだ。
なぜ僕らは「AIプロンプト」をこんなに”難しい”と感じるのか?
そもそも、なぜ「AIプロンプト」はこんなに難しいんだろう。 理由はたぶん、僕らがAIを「完璧すぎる部下」か何かだと勘違いしているからだ。
「的確な指示(プロンプト)さえ出せば、100点の答えが返ってくるはず」。 そう信じているから、「的確な指示」が出せない自分にモヤモヤする。「AI活用」とは、まるで「いかにAIをうまく騙し、おだて、最高のパフォーマンスを引き出すか」という高度なゲームみたいになってる。
その結果が、「プロンプトエンジニアリング」という、ちょっと大袈裟な言葉の流行だ。 でも、僕らが本当にやりたいのは、そんな「AI使い」の達人になることじゃなくて、日々の仕事をちょっとラクにしたり、新しいアイデアのヒントをもらったり、そういうことだったはず。
その壁、「プロンプトエンジニアリング」ごとAIに任せてみないか?
その「プロンプトが難しい」という壁。面白いのはここから。
「そうだ、この『難しい』という悩みごと、AIに相談してみよう」 つまり、AIに「AIの使い方」を教えてもらう。さらには、AIに「AIを動かすためのプロンプト」そのものを”自動化”させてみる。
AIを「指示する対象」から、「一緒に考えるパートナー」として扱う。この発想の転換が、想像以上に面白かったんだ。
僕が試した「AI活用」の具体的なステップ
僕が実際に試したのは、このブログ記事の素案を作るプロセス(もちろん、この記事もAIと一緒に作ってる)や、業務でのチラシ作りだった。
ステップ1:AIに「先生」になってもらう(Deep Researchでの調査)
まず、僕はGeminiのDeep Research機能(※)を使って、AIに「先生」になってもらった。 「SEOに強いブログ記事の書き方って、どういう手順でやればいいの?」 「センスのいいチラシを作る前に、決めておくべきことって何?」 (※Deep Research:Gemini Advancedの機能で、複雑なリサーチを深く実行してくれる)
AIは、その道のプロが書いたような詳細なレポート(手順、フレームワーク)を返してくれた。ここまでは、まあ「賢い検索」の延長だ。
ステップ2:AIに「AI用のプロンプト」を”自動化”させる
ここからが本題。 僕は、さっきAIが作ってくれた「良いブログの書き方レポート」をAI自身にもう一度見せて、こう頼んだんだ。
「ありがとう、よく分かった。じゃあさ、今あなたが教えてくれた『良いブログの書き方』の手順に沿って、実際にブログ記事を生成できるAIを作るための”プロンプト”を作ってくれない?」
できた。「プロのブロガー」として振る舞い、特定のステップ(ペルソナ設定、キーワード立案、構成案作成)を踏んで記事を生成するための、詳細な指示書(プロンプト)を作ってくれた。
「プロンプトエンジニアリング」って、僕らが必死に考えるものだと思ってた。でも、AIは自分が教えてくれた「あるべき姿」に基づいて、自分を動かすための「プロンプト」すら自動化してくれたんだ。
ステップ3:業務(チラシ作り)でも「AI相談役」が活躍
この方法は、ブログ記事だけじゃなかった。 業務で内製するチラシ作りでも、「チラシ作りの考え方」をAIに調べさせ、その考え方に沿って「ペルソナ設定」や「キャッチコピー」を相談する「AI相談役(Gem)」を作った。
結果は期待どおり。 ガイドライン(AI自身が調べてきた『あるべき姿』)に沿ってくれるから、的外れな回答が減って、すごく満足いくアウトプットが返ってくるようになった。
結論:「プロンプトエンジニアリング」は死なない。ただ”民主化”されるだけだ。
さて、ここで最初の問いに戻ろう。 「プロンプトエンジニアリング」はもう要らないのか?
僕の結論は、「ノー」だ。でも、その意味は大きく変わっていく。
これまで「プロンプトエンジニアリング」が一部の専門家や、感度の高い人たちの「技術」だったとしたら、これからは違う。 AIに「あるべき姿」を学ばせ、AIに「プロンプト」を作らせることで、誰もがAIのポテンシャルを最大限に引き出せるようになる。
つまり、AI自身の手によって、「プロンプトエンジニアリング」は”民主化”されるんだ。 専門家がゼロから呪文を考える時代から、AIが作った呪文を僕らが「これでOK?」と確認・調整する時代になる。
AI時代に必要なのは「完璧な指示」より「まず試す」マインドセット
僕らがこの「AI活用」の波に乗るために本当に必要なのは、「完璧なプロンプト」をひねり出す能力じゃない。 それは、「とりあえずAIに相談してみよう」という気軽なマインドセットだ。
AIを「間違うはずのない完璧なツール」として恐れるんじゃなく、「ちょっと物知りな相談パートナー」くらいに思うこと。 「プロンプトが難しい」? なら「プロンプトの作り方、教えてよ」ってAIに聞けばいい。ミスっても大丈夫。だってAIは怒らないし、何度でもやり直せるんだから。
「プロンプトエンジニアリング」という言葉の重さに圧倒されて動けなくなるより、まずは気軽にAIに話しかけてみる。 AI時代への適応って、案外そういうシンプルなことから始まるのかもよ。